2017.03.21
冷凍手毬寿司の挑戦から見えたこと【後編】
なぜシンガポールだったのか。あらためて直面した課題とは。
アメリカで頓挫した「冷凍手毬寿司」の新たな展開先が
シンガポールになった理由は? そしてその顛末は?
1年間のプロジェクトを終えて、今あらためて取り組んでいる
独自のプロジェクトにも迫る。
2017.03.21
なぜシンガポールだったのか。あらためて直面した課題とは。
アメリカで頓挫した「冷凍手毬寿司」の新たな展開先が
シンガポールになった理由は? そしてその顛末は?
1年間のプロジェクトを終えて、今あらためて取り組んでいる
独自のプロジェクトにも迫る。

1980年生まれ。11〜18歳までアメリカ・サンディエゴで過ごす。慶応義塾大学卒業後、株式会社電通に勤務。2012年より株式会社THINK GREEN PRODUCE。2015年よりTOKYOEDGE.を立ち上げる。食やファッション、カルチャーを軸としたコンテンツの企画、開発、プロデュースを行う。またメディア開発やPRなどのプランニングも行う。
Paragraph 01

「8割がた終わっていた」という引地さんの仕事で、「ヴィーガン手毬寿司をどう海外展開するか」というストーリーは出来上がっていた。アメリカが頓挫した時、彼らが考えたのは、「ならばこのストーリーが当てはまる別の国は?」ということだったのだ。
つまり、
・パーティー文化が根付いておりケータリング需要が高い
・貿易の障壁が低いところ
2つ目は、アメリカでの失敗を経て追加された、非常に強い条件だろう。
「シンガポールは外食が多い。都市部は国際化されていて、みんなパーティーも大好き。食への感度も高いんですね。リサーチしてみたら、驚いたことに、シンガポールの高級寿司店では、その日築地に朝上がったネタを、夕方には食せるそうなんです。もちろんめちゃくちゃ値は張ります。でも、そうした需要がちゃんとある。だから、後々交渉し始めた時にそういう注意をされました。『ハン? 冷凍寿司だって? 俺らは下手な日本人よりよっぽどいい寿司食ってるんだぜ!』って(笑)」
繰り返しになるけれど、手毬寿司の勝負ポイントはそこではないのである。
「僕らは超ハイクオリティの寿司に戦いを挑もうとは思っていない。またシンガポールの普通の人たちが楽しんでいる近所のローカル寿司のシェアを脅かそうとか、あるいは向こうで独自に発展したオリジナルの、いわばカリフォルニアロール的なものに取って代わろうとは一切思っていないわけです。ただ、ある程度のクオリティを担保していてビジュアルもかわいくて“Japanese Traditional Party Finger Food”である寿司を提供したいと。“その価値観に当てはまらない人たちに無理やり食べてもらおうとは思ってないです”っていう姿勢を明確にしながら交渉していきました」
Paragraph 02
話を事業の海外展開と考えるから面倒なのであって、身近なことに例えると、極めてわかりやすい。
「そもそも興味のない他人に興味を持てというのは、日本人同士だったとしても、たとえ相手が友だちだったとしても難しいですよね? 食事にこだわりのない友だちを、一人2万円する評判のフレンチのお店に誘いませんよね? 年配の方向けの高級懐石のお店を『王様のブランチ』で紹介してもらおうとは思わないじゃないですか。売る側にお金と体力があればいいけど、僕たちにはバジェットが全然ないので、誰に向けて何をどう売るかを決めてかからないと、自己満足で終わることになる」
例えば、今回のシンガポールの件でも、地方のスーパーで販売するという話があった。集客や売上は見込めたが見送った。
「仮に1日2万人来て3000食がハケたとしても、僕らがやろうとしているケータリングのことは伝わらないし、そもそもこれが“Japanese Traditional Party Finger Food”であるということは認知されないだろう、と判断したんです」
記録上は、シンガポールに行ってこれだけの人々にアピールした、ということになるかもしれないが、目標に対しては一歩も近づいていない。まさに自己満足なのだ。
引地さん、2014年10月にシンガポール視察に訪れているが、「実際、商談にまで至ったところはとても少ない」と笑う。だって闇雲に誰かに会ったり、無理やり商品を置いてもう必要がないわけだから。繰り返しになるかもしれないが「手毬寿司をシンガポールに売るまでのストーリー」が、完全に順序立てて脳内に組み立てられていて、あとはそれに則っていけばいいだけだった。それは展開する先がアメリカからシンガポールに変わっても大差ないのだ。
国内である程度目処を立て、シンガポールで日本人向けメディアを発行している会社や現地のローカルスーパーと“日本マーケット”のようなイベントを行う会社、「クールジャパン」を標榜するようなイベントを展開しているPR会社や制作会社、日本食レストランを現地に誘致している会社などと商談した。自分たちのストーリーに合いそうなところと「お見合い」したのだ。そして実際に現地に行き、それが実現可能かを体験しにいったのだ。
結局、組むことになったのは、「一般社団法人 日本外食ベンチャー海外展開促進協会」(=JAOF)。
シンガポール中心部に、翌年オープン予定の日本食レストランにメニューとして組み込む話がまとまったのだ。
「レストラン側がランチとディナーのメニュー開発をするなかで、手間をかけずローコストでいいメニューを出そうという時に手毬寿司が目にとまったんです。店のオープニングレセプションでPRとして使ったり、定期的にメニューに入れるという条件で買い上げてくださいという話になったんです」
しかし、JAOFが手がける『TAKI Japanese Dine & Sake』レストランのオープニングは当初の予定だった2015年2月から、約1ヶ月遅れることが判明する。そこで三嶋フーズ繋がりでもある彫刻家の大平龍一さんをオープニングレセプションにブッキング。大平さんは、西行法師の詩を芸術的なルーツに、炭化させた木彫にゴールドをあしらったり、打ち出の小槌に大黒様をモチーフにした作品などを発表している気鋭アーティスト。「手毬寿司がジャパンコンテンツであるのと同じように、日本文化を発信できる専門家に協力してもらいたいと思ったんです」
オープニングイベントにはシンガポールのフードコーディネーターやPR担当者などが多数参加し、“Japanese Traditional Party Finger Food”としての手毬寿司を堪能した、という。
*1
日本食文化と日本の食材の海外展開のためのコンサルティングやブランディングを行う団体として2013年に設立。その翌年にはクールジャパン機構と共同の取り組みで、シンガポールにジャパンフードタウンの企画を行っている。
一般社団法人 日本外食ベンチャー海外展開促進協会
日本・東京
住所:東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビル7F
TEL 03-6890-2042
http://www.jaof.jp/
*2
2014年に日本で行われた若手料理人コンクールで準決勝進出経験のある新田周平がディレクターを務める日本食レストラン。築地から空輸で調達するなど食材へのこだわりも強く、本格的な和食を提供している。
TAKI Japanese Dine & Sake
Paragraph 03

ここまで狙いは外していなかった。だが、その後、このレストランに三嶋フーズの手毬寿司は定期的に納入されていない。
「実は三嶋フーズさんの特徴であるプロトン凍結の状態をどうキープしてシンガポールの現場まで届けるかが問題になったんです。プロトン凍結のキープ自体はそんなに難しい事では無く、一旦凍らせてしまえば特殊な管理は必要なく-18℃以下の温度管理だけで良いのですが、その環境を維持するのが、日本以外では難しいと分かったんです。国内の流通管理では問題なく、工場出荷から神戸港、そこからシンガポールに向けて出港するまでの出国の手続きの間、そして出国後の船の上での保管まではクリアできたんですが、シンガポールの港で検疫を通過するまでの間と、その後、営業所が受けとってからお店に入れるまでの間で、冷凍状態をキープするのが難しかった。正確にはこっちの管理が及ばない。発泡スチロールに入っているので完全に溶けるわけではないもの、クオリティの担保はできなかったんです。」
三嶋フーズの冷凍技術は、武器であると同時に、誰もが簡単に真似できるものではなく、そこが逆に輸出の際の課題になったわけだ。そして、「いかにベストな冷凍状態を維持するか」という点に関しては、もはやテクニカルな部分の問題であり、引地さんが手出しできる話ではなくなっていた。
「手持ちで輸出するとか、航空便ということも考えましたが、コストが合わなかったんです」
そうこうしているうちに、プロデューサーとしての任期は終了してしまった。
が、引地さんと三嶋フーズで作ったヴィーガン手毬寿司は生きているというのだ。それは国内での展開。
シンガポールのプロジェクトを進めながら、14年11月の段階で、京都で試食会を行っていたのである。繁華街のど真ん中にあって、今は廃校になってしまった小学校を借り、東京からヘアメイクアップアーティストやデザイナー、イラストレーター、モデルなどを招き、かたや地元京都の陶芸家や商店会の重鎮を招待して。
「これは国内でのPRという意味合いが強かったですね。もちろんシンガポールに売る際の資料作りという要素もありましたが、来てもらったのはいわゆるインフルエンサーたち。試食会という名の下に手毬寿司をSNSでアップしてもらう。で、“何これカワイイ!”的なリアクションを得ることは十分に意識していました。それをしかも京都でやると、よりアップする理由になるしローカル感をアピールできる。その上、ヴィーガンである。ケータリングできる。シンガポールに持って行くらしい、ということがネット経由で拡散するといいなと思ったんです」
この仕掛けが、きちんと開花したのである。
「そこが僕らのもう一つの思惑でした。海外展開することで、同時に国内のケータリング事業も活発化させたいという。それはしっかり結果が出ていると思います。もともと三嶋フーズはウェディングでのケータリングもやっていたんですけど、そちらでの需要もひっきりなしだと聞きます。僕自身はもはや事業としては関わっていませんが、手毬寿司の問い合わせをいただくたびどんどん紹介してますよ」
シンガポールの件を踏まえて引地さんが強く実感したのは、「削ぎ落とすことの重要性」。自分が何を売りたいかに固執しすぎて、あれもこれもと付け加えていくのはうまくないという。
「“あなたってどんな人ですか?”って尋ねられると、なかなかうまく答えられないでしょ。でも、“隣にいる友達のことを説明してください”って言われると、ポイント絞って語れますよね。それと似てる気がするんです。何が必要で、何がそうでないか。どこから優先順位をつけていくか。自分のことだと、ああいう要素もこういう要素もある! って思い込んじゃうんだけど、客観的にみることができれば、何を求められていて、何を言えばいいのかを簡潔に提示できたりする。それこそ外部のプロデューサーと組む意義だと思います。」
Paragraph 04

バジェットで勝負することのできないピンポイントなマーケティングの場合、自分たちの「こだわり」が相手にささる「こだわり」なのか、と客観的に見直すことが大切だと引地さんは言う。
「海外になにかを持って行く際、本当に“本物”を持っていかなくちゃいけないのかっていうのが最初の議論ですよね。僕はそれが伝わるとは限らない、といつも思っています。」
それを11歳で実感したという。つまり、サンディエゴでの転校初日。アメリカの子どもたちは、ランチとして茶色い紙袋にピーナッツバターを塗ったトーストやらサンドウィッチやらを入れて学校に持ってくる。お昼休み、当時、学年で唯一の日本人だった引地少年の動向にクラスは興味津々だった。で、彼が紙袋から出したのは……おにぎりだった。
「そしたら“Wow~, SUSHI!!!”って。隣のクラスのヤツまで見に来る騒ぎになって(笑)。“やっぱりオマエらは毎日寿司を食うのか!?”と。日本人の僕からすれば、それは確実に寿司ではないんですよ。おにぎりだから。でもそれが海外のリアルなんです。仮に僕が持っていったのが銀座『かねさか』の握りでも、アメリカのスーパーで売っているカリフォルニアロールでも、彼らにとっては“SUSHI”なんですね。これも寿司だけど、あれも寿司。今、向こうに日本のものを持っていく事業の多くは、相手が日本のことを知っている、もしくは好き前提で企画されているものが多い気がする。でも、そうじゃないひとのほうが何倍もいるんですよ。だからと言って彼らは日本に興味がないんじゃなくて、きっかけがないだけ。たぶん小学5年生の僕が「ちがう、これは寿司じゃない!本物の寿司はこれだ!」と言って銀座『かねさか』の握り寿司を出したら、「なにこれ!気持ち悪い!!」ってなったかもしれませんよね。本物は本物かもしれないけど、リアルではない。こういう時必要なのはリアリティのほうなんです。」
その思いが、今、引地さんが主宰しているファッショナブルな展示会場につながるわけだ。
題して『NEWWESTS Chronicle』。引地さん自身が知り合ったカリフォルニアと西日本、アメリカと日本の「西」で活動するクラフトマンたちと、その仕事を紹介するもの。なにがどこでいくらで買えてどんな風に流行ってるのかとかいう「情報」ではなく、どんなヤツがどうやって作っていて、どんな思いを抱えてるのかを、すべて引地さん自身が現地で「体験」してきて紡ぎ出している。
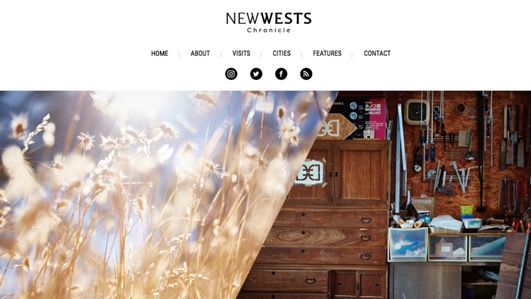
「僕の家族のルーツが久留米なんです。おじいちゃんが住んでて毎年里帰りしてたんですけど、3年前に亡くなって、墓参り以外くる理由がなくなるなと。それで飲みに行く友だちが欲しいなと思ってたら、たまたま都内のイベントで知り合った荻野みどりさんが久留米出身だったんです。日本にココナッツオイルを広めた第一人者でオーガニック食品会社の代表なんですけど、「最近、久留米って面白くないですか?」って。たしかにおしゃれなスニーカー屋さんだったり、コーヒーロースターができてたり。さらに久留米の周りにはたくさんの職人の街があって、そこにもまた面白いことをやってる若者たちがいて。みんな言っていることは同じ。原点回帰とか地産地消とか。それ、カリフォルニアの奴らもまったく一緒の事を言ってる!って。」


つまり、「本当に知りたきゃ会いに行こう」と。
「今や手元のスマートフォンでなんでも調べられる。知識に近い情報はだれでもどこでもいくらでも手に入る。そのお陰で世界との精神的距離は近くなっている。次に必要なのはもう片方の手で握手することなんじゃないか、と。現地に行って経験することでしかわからない「体験」は確実にあって、その情報と体験を西日本とカリフォルニアの友人たちと共有するのが今の僕のプロジェクトです。2017年春にはサンフランシスコでポップアップショップをやります。」

*1
引地かいがディレクターを務める、アメリカ西海岸と西日本の若きクラフトマンをつなぐプロジェクト。地産地消や伝統的技法、人や自然との有機的なつながりを大事にする、ふたつのエリアの共通の価値観を「情報」と「体験」で伝えるメディアサイトも展開。
NEWWESTS Chronicle